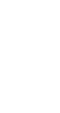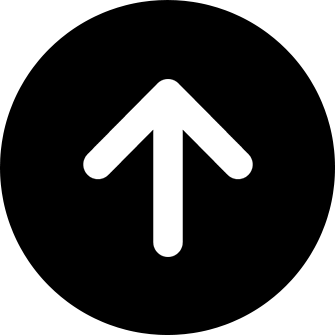こんにちは、ABBYです。
内戦も終わり、近年ビジネスでも注目を集めているスリランカ。
スリランカへ進出する日系企業は年々増えているそうですが、スリランカで歴史の長い日系企業といえば、日本を代表する陶磁器メーカーの「ノリタケ(Noritake)」が有名です。
スリランカの友人たちいわく、ノリタケはスリランカ人なら誰でも知っている超有名ブランドで、品質やデザイン性の高さから結婚式などの特別な時の贈り物に使われることも多いのだとか。

そんなノリタケがスリランカに食器製造工場を設立したのは、スリランカがまだ今ほど注目されていなかった1972年。以来、多くの雇用を生み、現地の人材を育てながら、この地で食器の製造を続けているそうです。

現在、ノリタケの主力製品は自動車部品などの研磨に使う工業用の砥石やセラミック原料などで、意外にも洋食器の売上は全体の10%程度。
それでも食器の製造を続ける理由は、食器は工業製品とは違い一般消費者の手に渡るため、世界中の人にノリタケブランドを認知してもらいやすいこと、またノリタケの原点ともなる研磨技術を食器製造の中で研究開発することで、ノリタケ全体の技術力を高めていく狙いもあるのだそうです。
今回は事前にお願いをしてスリランカのノリタケ工場を見学させていただきました。
(許可を得て撮影をしています)
世界中のノリタケ洋食器を生産する巨大工場

ノリタケの看板や製品はコロンボ市内でもよく見かけますが、その工場はというと、実は仏歯寺で有名なキャンディからさらに車で1時間ほどの、本当にココ?(←失礼、笑)というような山間の村にありました。

エントランスを抜けてすぐ目の前に現れたのは巨大なメイン工場の建物。ここでノリタケ製の全洋食器の約90%を製造しているそうです。

工場脇にあった陶器の原料となる素材。

泥漿(でいしょう)を使った成形工程。泥漿とは複数の素材と水を調合した液体物で、それを型に流し込んで水分を絞り、陶器のもととなる粘土をつくっていきます。

形を整えた粘土を高温で乾燥させ、型から出したところ。

こちらはティーポットの取っ手をつけているところ。すでに完成形に近く見えますが、まだまだこれから。

釉薬(ゆうやく)と呼ばれるガラスの成分を陶器に吹き付けます。表面にツヤが出て、陶器の防水や防汚にもなるそうです。

約1300度の高温で焼き上げる本焼き。

模様づけはやり直しのきかない1発勝負の熟練技。スリランカ人は手先の器用な人が多く、細かい作業の精度がとても高いそうです。

最後に一つ一つの出来をチェックします。このチェックがかなり厳しいそうで、中には素人の私には一見どこがNGなのかわからないものも。


比較的分かりやすいものを選んでみましたが、気にならない人なら充分使えそうなレベル。
はじかれた製品の一部は、工場の隣にあるノリタケファクトリーアウトレットショップ(Noritake Factory Store)にて、お手頃価格で販売されています。

無事にチェックを通過した製品たちは、丁寧に梱包され、コロンボ港から世界各地へと旅立っていきます。

ちなみに、スリランカではランチ休憩以外に、午前と午後にお茶の時間があり、ノリタケ工場でもその文化を取り入れているそうです。
みなさんノリタケのティーカップでスリランカ産の紅茶を飲みながら、オープンテラスで談笑されていました。なんとものどかで優雅な時間。

現地化のお手本
過去にも他のアジアの国々で工場や職場を見学させてもらったことがあるのですが、まずノリタケの工場は敷地内も工場内もとにかく清掃・整頓されていてきれいなことに驚きました。急に決まった見学にも関わらず、一通り見せても大丈夫ということは、このきれいな状態が日常であるということ。(急な来客で慌てて掃除をはじめる誰かさんとは違うようです、反省。笑)
あと環境がいいです。最初は田舎だなんて失礼なことを思っちゃいましたが、いわゆる工業地帯だと工場が密集していたり大気汚染問題があったりなど、どちらかというと暗いイメージになりがちなところ、ここは外に出ると澄んだ空気と開放的な景色が広がっていて、精神的にも労働環境としても”豊か”な感じがします。
また、どこぞの国でありがちなお金のために働かされているという雰囲気もなく、スリランカ人スタッフからは自分たちは世界ブランドをつくっているというプライドのようなものを感じたのも印象的でした。なんというか、目や顔つきが違うんですね。
スリランカ人は真面目とよく言われますが、一方で植民地時代や内戦の影響からか、仕事においては指示待ちで受け身であったり、長期的なキャリアビジョンを設計することが苦手な人も多い、という話も聞きます。
その点、ノリタケ工場は進出から40年以上の歴史の中で、スリランカ人スタッフが主体的に働きたいと思える環境や教育システムを確立し、無理なく自然なかたちで浸透させていっている、そんな現地化の好例ではないかとも感じました。